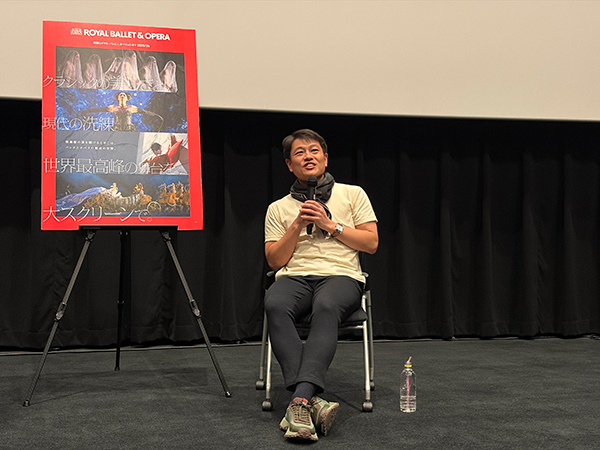コラム
日本出身のプリマ金子扶生がシンデレラを演じて絶賛された、ロマンティックでファンタジックな舞台が好評のためアンコール上映!
英国ロイヤル・バレエで長年愛されてきた名作の中の名作『シンデレラ』
心優しい人は報われて素敵なことが起きるというおとぎ話の魔法が、観る者に夢と希望とときめきを与えてくれる、みんなが大好きなフェアリーテイル『シンデレラ』。
数ある『シンデレラ』のバレエ作品の中でも、もっとも人気があり日本の観客にも親しまれている名作が、ロイヤル・バレエの創立メンバーである巨匠フレデリック・アシュトン振付の『シンデレラ』です。箒をシンデレラのパートナーに見立てたデュエット、男性ダンサーが女装してコミカルに怪演する義理の姉妹たち、四季の精たちのソロや星の精たちのきらめく群舞が特徴です。プロコフィエフの少しダークさを感じさせながらも美しいスコア、アシュトン特有の軽快な「フレッド・ステップ」が盛り込まれた振付、英国らしいおおらかなユーモアのセンス、そして心温まる余韻を残すファンタジックな終幕など、魅力あふれる名作として1948年の初演から英国ロイヤル・バレエで長年愛され、最も重要なレパートリーとして長年にわたって踊り継がれてきました。今ではアメリカン・バレエ・シアターや新国立劇場バレエ団など世界中で上演されていますが、本家ロイヤル・バレエの上演は格別です。
アカデミー賞衣裳賞受賞デザイナーらが手掛けたエレガントで華やかなプロダクション
2022年、初演75周年を記念してロイヤル・バレエではおよそ10年ぶりに待望のリバイバルとなった『シンデレラ』は舞台装置や衣裳も一新されての新プロダクションとなりました。『となりのトトロ』のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる舞台版でローレンス・オリヴィエ賞を受賞したトム・パイによる、花々が咲き乱れるガーデンパーティをイメージした華麗な舞踏会場が印象的な舞台装置、6度アカデミー賞衣裳デザイン賞にノミネートされて2007年にはオスカーを手にしたアレクサンドラ・バーンによるオートクチュールのような洗練されたエレガントな衣裳も大きな魅力です。
日本が生んだシンデレラ・ガール、プリマ金子扶生の輝き/芸達者なダンサーたちにも注目!
明るく健気で清らかな心を持つシンデレラを演じるのは、ロイヤルを代表するプリマ・バレリーナへと躍進を続けて世界中の劇場にもゲスト出演している、まさに“シンデレラ・ガール”として輝く金子扶生。難しいステップも軽やかに鮮やかにこなし、前向きに運命を切り開くヒロインを好演しています。王子役のウィリアム・ブレイスウェルは優しくノーブルな貴公子役がぴったりで、金子とのパートナーシップを待ち望んでいる現地ファンの熱望に応えての今回の共演となりました。颯爽としたブレイスウェル王子のソロ、そして2幕の舞踏会での二人の想いが高まるパ・ド・ドゥは甘美でロマンティックなことこの上ありません。
シンデレラを導く仙女を温かみのある演技で演じるのは、演技にもテクニックにも優れ、この後の『くるみ割り人形』シネマでは金平糖の精を演じるなど目下絶好調のマヤラ・マグリ。この作品のもう一つの主役と言えるほど暴れまわり強烈な印象を残す“ファッション中毒のInstagramインフルエンサー”のような義理の姉たちは、ロイヤル・バレエを代表する名役者ベネット・ガートサイドと、王子役も演じる端正なダンスールノーブルとして定評のあるジェームズ・ヘイが挑み、観客を爆笑の渦へと導きました。特にジェームズ・ヘイは、『リーズの結婚』ではリーズの母親役シモーヌ役の演技と軽快な“木靴の踊り”で大評判となり、この後のシネマ『くるみ割り人形』では魔術師ドロッセルマイヤー役デビューを飾って新境地を開くなど、最近の活躍ぶりが目覚ましく、その芸達者ぶりから目が離せません。
さらに驚くほどの高い跳躍や見事な回転技、愛嬌のある演技で魅せる“王子のたった一人の親友”である道化役には、超絶技巧を誇る若手の五十嵐大地、四季の精のうち「夏の精」をプリンシパル昇格も期待される佐々木万璃子が詩情豊かに踊るなど、多くの日本出身のダンサーが活躍を見せています。
人気ダンサー、ギャリー・エイヴィスの姿を観る最後の貴重な機会
この『シンデレラ』上映では、ナビゲーターをプリンシパルキャラクターアーティスト/指導者のギャリー・エイヴィスが務め、舞台裏の様々な場所から作品の魅力をわかりやすく伝えています。その演技力と親しみやすい人柄で日本でも人気が高かったエイヴィスは昨年11月に惜しまれながらロイヤル・バレエを引退したため、これが彼の姿をスクリーンで観られる最後の機会となります。
世界トップクラスのスターダンサーたちによる、ときめきとロマンと笑いに満ちた華やかで夢いっぱいのバレエ作品は、冬の寒さを吹き飛ばして温かい気持ちにさせてくれるに違いありません。ロンドン・コヴェントガーデンでのときめくおとぎ話の魔法を、お近くの映画館で。